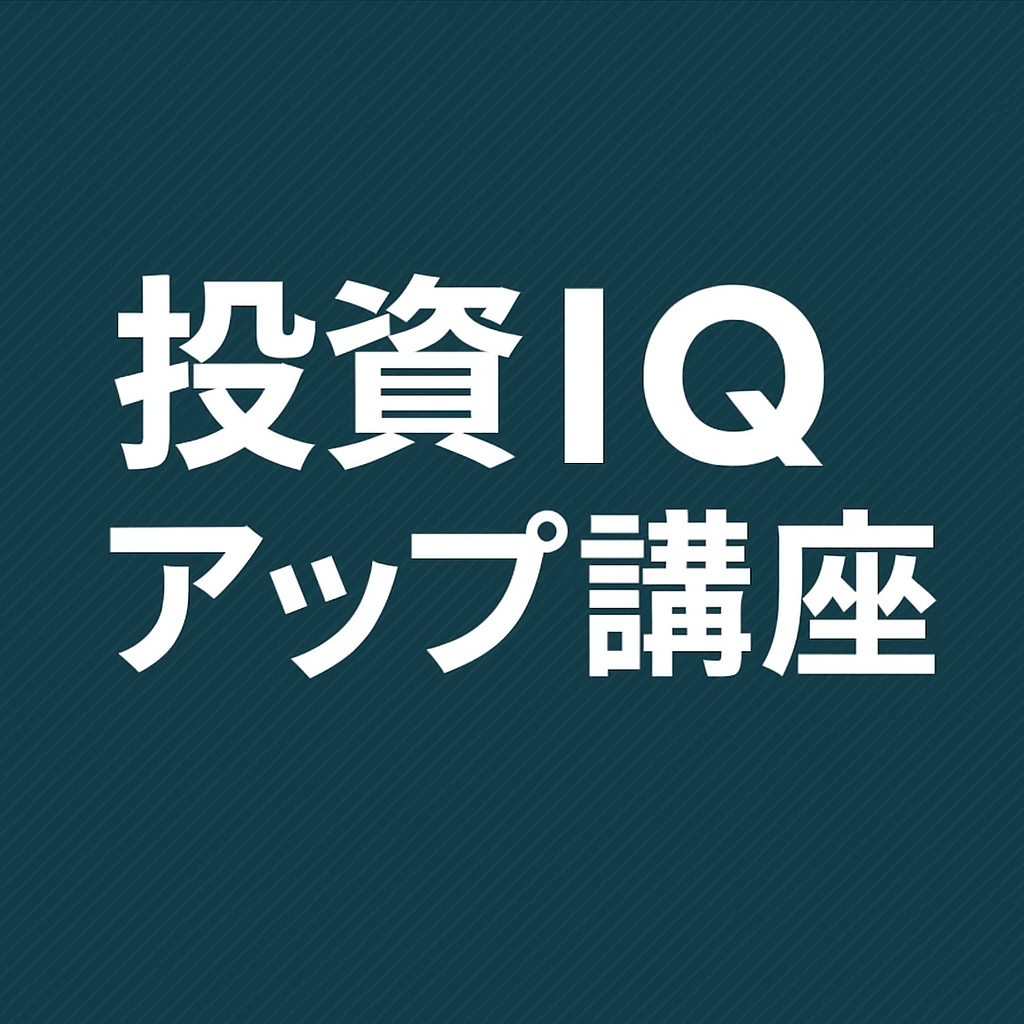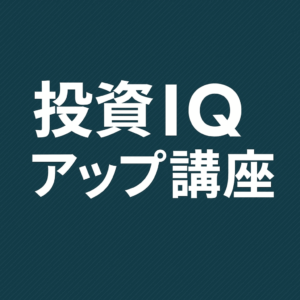「円安が進んで輸入品が値上がり」「円高で海外旅行が安くなる」――ニュースでよく耳にする為替の動き。
でも、その背景にある理論をしっかり理解している人は少ないのではないでしょうか。
今回は為替を読み解く基本理論のひとつ「購買力平価(PPP)」を学んでいきます。
目次
為替の基本:円安・円高とは?
- 円安:1ドル=150円 → 160円になると「円安」
(同じ1ドルを買うのに、より多くの円が必要) - 円高:1ドル=150円 → 140円になると「円高」
(同じ1ドルを買うのに、少ない円で済む)
円安=輸入品の値段が上がりやすい
円高=輸入品が安くなり、輸出企業に不利になりやすい
購買力平価(PPP)とは?
- 定義:通貨の価値は「モノやサービスを買う力」によって決まる、という考え方
- 理論式:
為替レート ≒ 各国の物価水準の比率
例(簡易版)
- 日本でハンバーガー:500円
- アメリカで同じハンバーガー:5ドル
→ 購買力平価から見た為替レートは 1ドル=100円
もし実際の為替が1ドル=150円なら、「円は割安」と判断できる。
歴史と実際の乖離
- ビッグマック指数(エコノミスト誌が発表):世界中のマクドナルドのビッグマック価格を基準に、各国通貨の割高・割安を比較
- 実際の為替は「金利」「貿易収支」「資本移動」など多くの要因で動くため、購買力平価とは大きく乖離することも多い
- ただし「長期的には物価の差で為替は調整されやすい」とされる
投資家の視点:為替と資産運用
- 為替は「国際投資のリスク要因」
- 円安時:外貨建て資産は円換算で増えるが、輸入物価上昇で生活コスト増
- 円高時:外貨建て資産は円換算で減るが、輸入品が安くなり購買力アップ
- 長期投資では「為替ヘッジ」や「国際分散投資」でリスクを調整することが重要
まとめ
- 為替=通貨の交換比率であり、円安・円高は生活と投資に直結する
- 購買力平価(PPP)は為替を理解する上での基本理論
- 実際の為替は短期的に乖離するが、長期的には物価水準に収束しやすい
理解度チェック(全3問)
Q1. 円安とはどんな状態を指しますか?
①円の価値が上がる状態
②同じドルを買うのに、より多くの円が必要になる状態
③海外旅行が安くなる状態
解答を見る
正解:②
円安=円の価値が下がる → 外貨を買うのに円を多く払う必要がある状態です。
Q2. 購買力平価(PPP)の基本的な考え方は?
①通貨の価値はその国のGDPで決まる
②通貨の価値はその国の物価水準で決まる
③通貨の価値は輸出額と輸入額で決まる
解答を見る
正解:②
PPPは「通貨の価値は物価水準によって決まる」という理論です。
Q3. 為替が長期的に購買力平価へ収束するとされる理由は?
①各国の物価水準の差が調整されるため
②中央銀行が強制的に為替を決めるため
③ビッグマック指数で自動的に調整されるため
解答を見る
正解:①
長期的には物価水準の差が是正され、為替も購買力平価に近づきやすいと考えられています。
次回予告
次回のテーマは 「第4回 株式投資と企業価値評価」 です。
PER・PBRといった基本指標の本質を押さえながら、株価がどのように決まるのかを解説していきます。