暗号資産の中でも「ステーブルコイン」は、法定通貨や安全資産に価値を連動させることで価格の安定性を持たせたデジタル通貨です。
世界中で決済や送金の新しいインフラとして注目されており、日本でも法整備が進み、ついに国内で正式に承認された円建てステーブルコインが登場しました。
本記事では、日本でのステーブルコイン承認の流れと、法制度、利用者にとってのメリットやリスク、そして今後の可能性について解説します。
ステーブルコインとは?
定義と種類
ステーブルコインは、暗号資産の中でも「価格の安定」を目的としたものです。
例えばビットコインは価格変動が激しい一方、ステーブルコインは「1ドル=1コイン」「1円=1コイン」といった形で法定通貨に価値を連動(ペッグ)させ、安定性を確保します。
種類としては、
- 法定通貨担保型:現金や国債などで裏付け
- 暗号資産担保型:他の暗号資産を担保にして発行
- アルゴリズム型:需要供給を調整するプログラムで価値を維持
があります。
日本における法整備の経緯
改正資金決済法の施行
日本では2022年に「資金決済法」が改正され、ステーブルコインを「電子決済手段」と位置づける法的枠組みが整えられました。
これにより、発行や流通、仲介に関するルールや責任が明確化され、利用者保護を前提に合法的に扱えるようになりました。
国内初の承認事例
2025年には、フィンテック企業 JPYC株式会社 が「資金移動業者」として金融庁から承認を受け、日本円と1:1で連動するステーブルコイン「JPYC」を正式に発行可能となりました。
裏付け資産として国債や銀行預金を保有し、分別管理を行うことで、利用者資金の安全性を担保しています。
規制のポイント
発行者の要件
ステーブルコインを発行できるのは、
- 銀行
- 信託会社
- 資金移動業者
と法律で限定されており、金融庁の監督下に置かれます。
裏付け資産の義務
円建てステーブルコインの場合、
- 国債や現金など安全資産で裏付け
- 発行残高と同額の資産を分別管理
- 定期的な監査・報告
が義務付けられています。
利用者保護措置
海外発行のステーブルコインについては、送金上限や滞留期間の規制が課され、利用者のリスクを最小化する仕組みが導入されています。
実用例と企業の動き
JPYCの取り組み
JPYCは2025年秋の正式発行を予定し、3年以内に発行額1兆円規模を目指すとしています。
さらに、ナッジ株式会社と連携し、クレジットカードの返済にJPYCを使える仕組み の導入を発表するなど、日常生活への浸透も始まりました。
海外ステーブルコインとの共存
国内では米ドル連動型のUSDCなども一部の取引所で利用可能となっており、今後は「円建て」と「外貨建て」のステーブルコインが共存し、個人や企業のニーズに応じた選択肢が広がっていきます。
メリットとリスク
メリット
- 為替リスクの回避:円建てならドル建て資産に比べて安定
- 決済・送金の効率化:24時間365日、即時で取引可能
- 金融包摂:銀行口座を持たない人でもデジタル送金が可能
- Web3との親和性:NFTやメタバース内での取引通貨として活用
リスク・課題
- 法制度が新しく、運用ルールや監督体制がまだ発展途上
- 裏付け資産の透明性や流動性への懸念
- ハッキングや詐欺などサイバーリスク
- 国際競争における遅れ:米国や中国、EUが先行している
今後の展望
日本におけるステーブルコイン承認は、Web3経済圏の基盤づくりとして重要な一歩です。
今後は、
- 決済・送金インフラとしての実用化
- NFTやメタバースでの流通拡大
- 国際送金や貿易決済への応用
など、幅広い分野での活用が期待されます。
同時に、利用者保護・規制の明確化・国際協調といった課題を解決することが、日本の金融イノベーションを前進させる鍵となるでしょう。
まとめ
- 日本では資金決済法の改正により、ステーブルコインの発行が正式に承認された
- JPYCによる円建てステーブルコインが国内初の事例として注目されている
- 利便性や経済効果が期待される一方で、法制度・セキュリティ・国際競争といった課題も残されている
- 今後、日本の金融インフラやWeb3の発展において、ステーブルコインは欠かせない存在となる可能性が高い



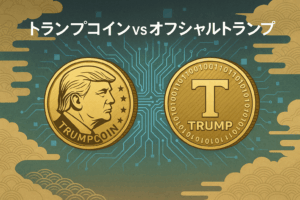



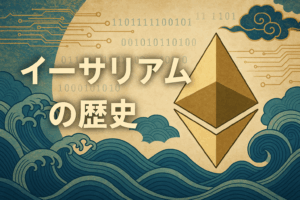

コメント